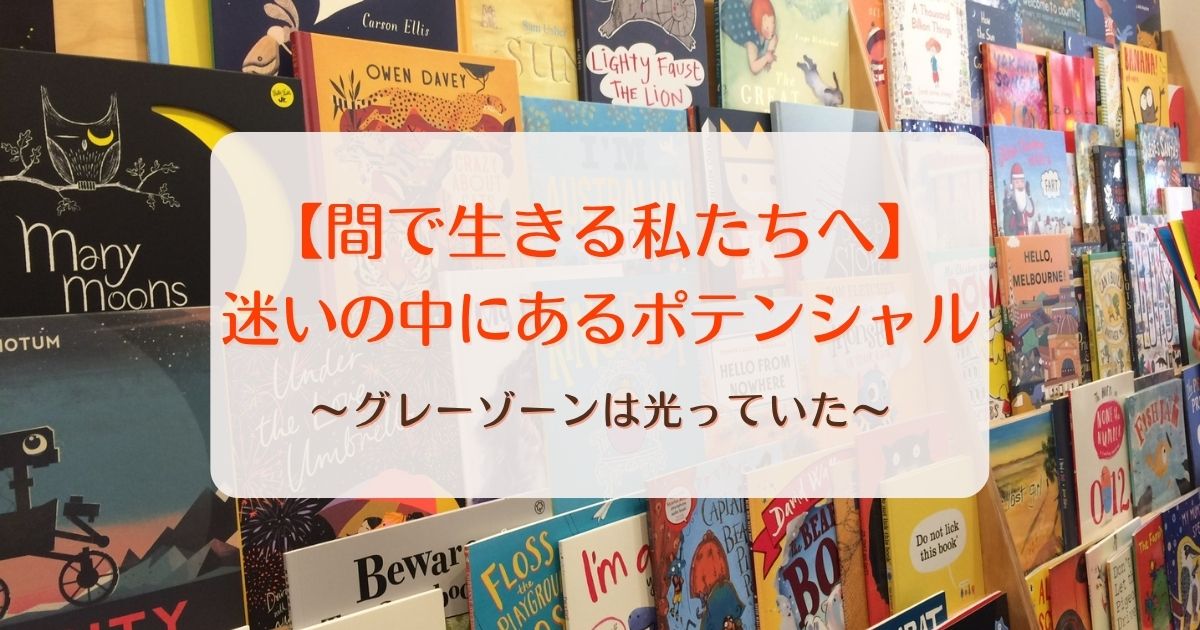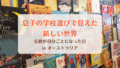こんにちは!英語圏での暮らしも早10年、オーストラリアの田舎で、オージーのパートナーと5歳の息子と暮らしています、Yukaです![]()
今回は、あるテレビシリーズを見て感じたこと、そこから得た気づきをシェアしたいと思います。
久しぶりに、作品のその世界観に没入し、かなりのインスピレーションを受けて、観終わった後もそのことについて考えさせられる。。。(この感覚、なかなか起きないので貴重なのです!!!)
せっかくこの感覚が起きてくれたので、忘れないうちにここに残しておきたいと思います![]()
![]()
「な〜んかモヤモヤする」「ウダツが上がらない感がある」「バシッと決められずに彷徨う感覚がある」よくわからないけど、漠然とこういった腑に落ちないような、そんな感覚を抱えている人にとって、今回の作品や気づきは、きっと何かのヒントになるはずです✨✨
カナダのTVミニシリーズ “Wayward”
以前このブログで紹介したオーストラリア映画は、25年前の作品でした。
そこでは「アジア人視点から見た、過去と今のオーストラリアの変化」について書きました![]()
![]()
▼アジア人に対しての時代の変化 — 嘲笑の時代から、共演の時代へ
https://yukalish.com/asian-visibility-evolution/
一方、今回ご紹介する Wayward は、カナダのTVシリーズで、2025年9月末にNetflixで配信された最新作です!8話完結の“ミニシリーズ” で見やすく、気づいた時には世界観に引き込まれ、あっという間に見終わってしまいました。ちなみに、*Wayward の意味は、もともと 「まっすぐに進まない」「型からはみ出した」「気ままな」といった意味があります。
日本語タイトルでは「背反の町」と訳されていました。
(余談ですが、しばらく“せはん”って読んでました![]()
![]()
「背反(はいはん)の町」、この背反とは、命令や規則に逆らう、とか、論理的に両立しえないこと(=矛盾)の2つの意味を持つ意味だそうです。まさに、英版オリジナルタイトルの“Wayward”の意味です。この作品に対してこのタイトルは、日英ともに、ドンピシャ!って感じです。タイトルのチョイスが絶妙だなと思いました。観たらきっとわかっていただけると思います![]()
![]()
※Wayward: difficult to control or predict because of wilful or perverse behaviour.
=「わがままな(ひねくれた)行動のせいで、コントロールしたり予測したりすることが難しいこと。」
謎多き小さな町、トールパインズ。
ジャンルはサスペンス、スリラーです。物語の舞台は、森に囲まれた小さな町・トールパインズ。
この静かな町で、2組の人たちの物語が同時に進んでいきます。ひとつは、妊娠中の妻と新しい人生を歩もうと引っ越してきた警察官の夫婦。もうひとつは、学校や家庭になじめず、居場所を探している思春期の少女2人。一見まったく別の世界にいるように見えるこの2組の物語が、やがてゆっくりと交わり、ひとつの真実へとつながっていきます。
警察官のアレックスと妻のローラは、新しい生活を求めてトールパインズへ。
このアレックスは、外見や雰囲気から性別を一言では説明できないような人物で、その中性的な存在感が、この作品のテーマ “境界と葛藤”とも深く響き合っています。
トールパインズは、ローラの故郷。
久しぶりに戻ってきたその町で、アレックスは次第に言葉にできない違和感を覚え始めます。
穏やかで美しいはずのこの町に、何かおかしい・・・。
一方、ライラとアビーという2人の少女。
「普通」や「正しさ」から少しはみ出した存在として、周囲とうまく馴染めずに生きています。
町には“問題のあるティーン”を立て直すと評判の施設、トールパインズ・アカデミーがあり、
アビーは両親の判断で、その寄宿学校へ強制的に入れられてしまいます。
そしてアレックスは、町に漂うその“違和感”をたどるうちに、アカデミーとトールパインズ全体に隠された、誰もが見て見ぬふりをしてきた、もうひとつの現実へと近づいていきます。
異様な世界観に包まれながら、鑑賞することになりました。ちなみにこういった展開が読めない作品は、私の大好物です。笑
Mae Martinの作品から得た気づき「間で生きる感覚」
鑑賞し終わって、心がざわつきました。
こんなに没入でき、心が揺さぶられ、考えさせられるのは、なぜだろう・・・?
そう思い、少し深掘りしてみたら……見えてきたんです!!!
このスッキリ感、ぜひここでシェアさせてください![]()
まず、この作品の中心人物であり、主人公アレックスを演じているのが Mae Martin(メイ・マーティン)。このMaeという存在が、とにかく気になって仕方ありませんでした。どこか自分と重ねてしまうような、不思議な感覚です。
そして観ているうちに、自然とこんな疑問が浮かびます。
「この人は女性なのかな?男性なのかな?」
物語の中でも、その“曖昧さ”や“型にはまらない存在”が巧みに描かれています。
たとえば、登場人物ライラ(問題児扱いされているティーンのひとり)が、アレックスにこう言うんです。
“I figured you weren’t from here. Queer people who grow up in small towns generally get the hell out… No offence, I’m Bi!”
和訳:
「この町の出身じゃないって、すぐわかったよ。
小さな町で育ったクィアの人たちは、大体さっさと出ていくからね。
あ、悪気はないよ。私バイだから!」
※ここで言う「クィア(Queer)」とは、従来の男女や異性愛の枠にとらわれない人々のことを指します。つまりこのセリフには、「小さな町では“普通”から外れた存在が居場所を見つけにくい」という皮肉が込められています
私は今回のこの作品で、Maeの存在を初めて知ることができたのですが、なんと主人公を演じているMaeが監督も務めていたのです!そしてMae自身が、ノンバイナリーという性の枠にとらわれない立場の人物。俳優であり、コメディアンであり、クリエイターでもあるMaeは、まさに“間で生きる人”。
そして気づいたのです。
私自身も、狭間で生きてきた人間なんだと。
日本とオーストラリアの文化の狭間。
日本語と英語の言語の狭間。
ASDとADHDの特性の狭間。
自由に生きたい自分と、「大人とはこうあるべき」という社会の価値観の狭間。
そして、アナログとデジタルの狭間の時代に生まれた世代。
……そしてなんと、Mae Martinも私と同じ歳でした。
私はいつも、どちらか一方ではなく、その間(あいだ)に生きてきた。
だからこそ、Maeの作品を見たとき、胸の奥が震えたんだなと、わかった時の感動。
“どこにも完全には属さない人間”の感覚。これが、この作品に美しく描写されていました。
Maeが作り出したWaywardの世界観
結局何が言いたいか?Wayward を観て気づけたことを、自分なりにまとめてみます。
「本音で生きる」も、実は“新しい型”に縛られていることがある
今の時代は「個人の自由」を掲げるあまり、
逆に“自由でいなきゃいけない”という新しいプレッシャーが生まれている気がします。
たとえば、昔は「副業は禁止!」と決まっていたから、
「ダメだからできない」で済んでいました。
でも今は「副業で好きなことをしよう!」と言われる時代。
……そう言われても、「じゃあ、何したい?」と聞かれて困ってしまう。
⬆️まさに、これです。
「性別にとらわれない生き方をしよう」
「自分の好きなことを仕事にしよう」
「自分軸で生きよう」
どれも一見ポジティブに聞こえるけど、
人によっては「それができない自分=ダメ」と感じてしまうこともある。
“自由”であることすら、いつの間にか“新しい型”になっているような、そんな感覚。。。
Mae はその“狭間”を描いているんですよね。
社会の枠から抜け出しても、今度は「自由という枠」に苦しむ人たちがいる。
→ 社会に合わせすぎると窮屈。
でも、個人の自由を突き詰めすぎると孤独。
なんとも皮肉な構図じゃないですか???![]()
その中間で、「どっちでもない自分をどう生きるか」という葛藤が生まれる。Mae Martin の Wayward はまさにこの「間(between)」のリアルを描いてくれているんですよね。
この感覚を、TVシリーズとしてここまで完成させてるMaeの世界観に、尊敬の意を。すごいなぁ。。。
そして、観ながら思うんです。
Maeも同じ“間”に生きる一人の人間として、こんなに堂々と表現しているのに、
つい「自分なんて…」と思ってしまいそうになる。
でも、それは—— No, No, No☝️![]()
じゃあ、落としどころはどこにあるのか???
それは、「狭間に生きる人にしか見えない視点」。
そこにこそ、ほんとうの自由があるのかもしれません。
「グレー」にこそ見える景色
狭間で生きるって、正直しんどいです。
どっちにも完全には馴染めないし、いつも少しズレているような感覚がつきまとうから。
でも、だからこそ見える景色があるんですよね。これ、本当にそう。
どちらにも属していなくても、両方の感覚を持っている。
だからこそ、どちらの立場にも寄り添える。
ここまで読んでくれているあなたには、きっと「共感力」があるはずです。
白か黒かじゃなく、その間にある“無数のグラデーション”を知っている。
片側だけでは感じられない痛みも、優しさも、両方を抱きしめられる。
それが、私たち「間で生きる人」の強さであり、美しさなんだと思います。
最近よく耳にする「グレーゾーン」という言葉。
これはまさに、その“間”に生きる象徴のようなものですよね。
障がい者でもなく、健常者とも言いきれない——一番苦しい領域だとされることもある。
でも、私はそこにもうひとつ加えたい!!!
その“グレーゾーン”の中には、❤️がある。
共感力。相手をわかろうとする気持ち。物事を深く探る好奇心。
そこには、たくさんの“beautiful mind”が詰まっていると思うんです。
グレーでOK![]()
グレーでウェルカム![]()
むしろ、グレーでラッキー![]()
![]() なんです!!!!
なんです!!!!
グレーでいることでしか見えない景色があるんです!
それを感じるんです。受け入れてください。
そして、感じたことを表現してください。
きっとあなたの中に眠る“beauty”が、静かに動き出します。
それでは、また次の記事でお会いしましょう!:)
Have a lovely day 🌿